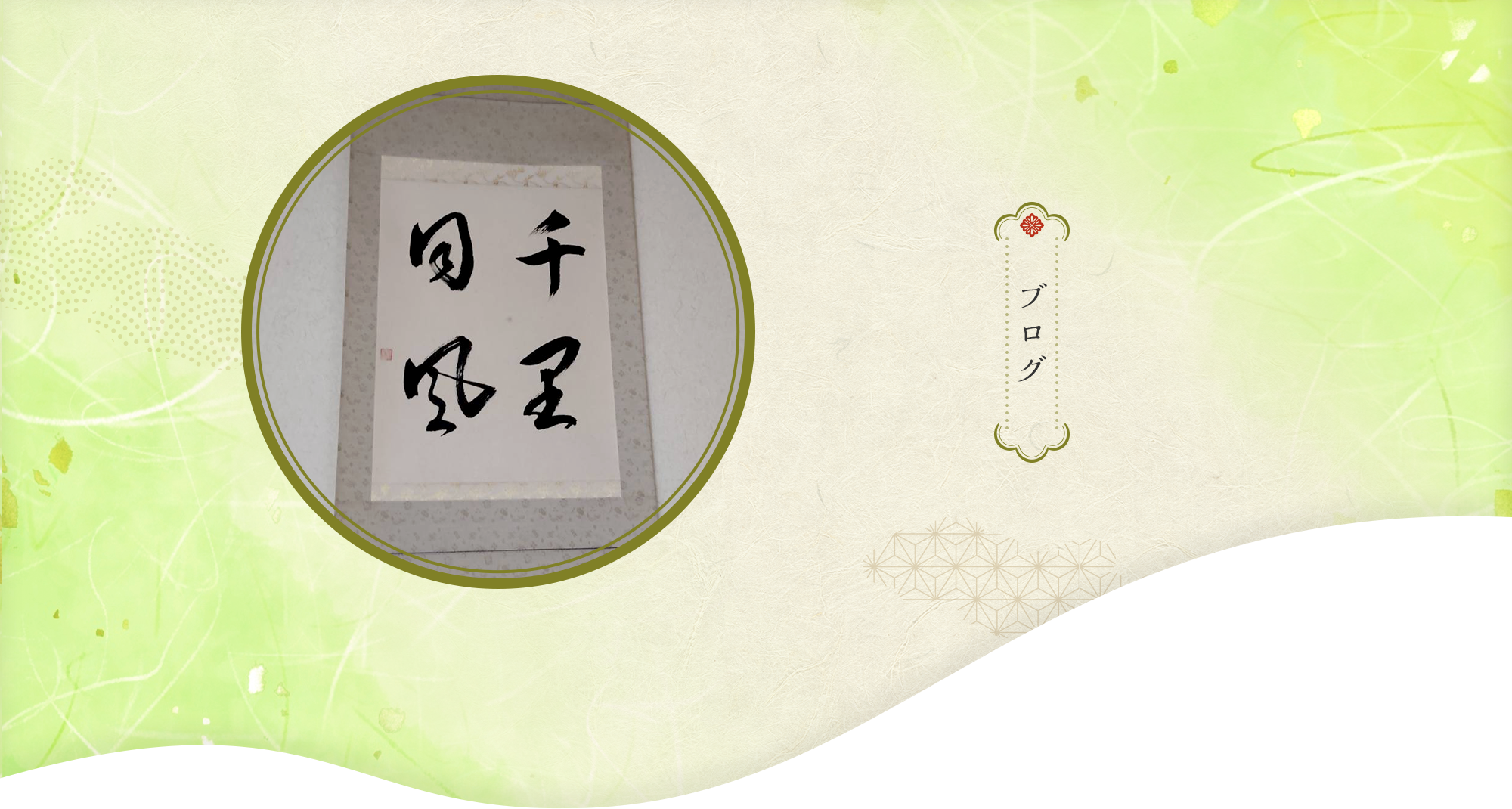今日、ようやく見てきました。
何も下調べもせずに見に行ったのですが、3時間の長丁場、深みのある、とても見ごたえのあるものでした。
下記記事を見つけました。
喜久雄は幸せな人生だったのか ――「国宝」連載を終えて 吉田修一
最終回を書き終えた今も、まだ喜久雄のことばかりを考えている。銀座の大通りで車のヘッドライトを浴びた姿を思い浮かべながら、彼は幸せだったろうか、幸せな人生だっただろうかと。 俊介を失ってからは、芸に精進するあまり、応援してくれる客の姿も見えなくなり、孤高の芸術家の常として最後はファンよりもアンチの方が多かったのかもしれない。とすれば、人気役者としては失格である。ただ、そんな不器用な役者の姿が、私には、父親の仇(かたき)を討とうと、朝礼の途中で駆け出したあの少年の姿にずっと重なっていた。 連載中、読者からお手紙を頂いた。そこにはあたたかい励ましの言葉があり、熱い拍手があった。孤立する喜久雄を、劇場の片隅で静かに応援してくださる真のご贔屓(ひいき)の方々だった。 彼が幸せだったのか、幸せな人生だったのか、いくら考えても、その答えが私には分からない。稀代(きたい)の女形の幸福というものが一体どんなものなのか、常人の私には思いも及ばない。ただ、三代目花井半二郎という役者に出会えた私は幸せだったと、今、心から言える。 今回の連載では、多くの方々にお世話になった。日々寄り添ってくれた担当者をはじめ、美醜のあわいを見事に挿絵で表現してくださった束芋氏、また歌舞伎の監修を引き受けてくださり、その豊穣(ほうじょう)な世界を丁寧に教えてくださった児玉竜一氏にはいくら感謝してもしきれない。 そしてなによりこの方、四代目中村鴈治郎さんとの出会いがなければ、「国宝」は生まれていない。 今から三年ほどまえ、歌舞伎役者を主人公にした小説を書こうと思っていると相談した初対面の私に、鴈治郎さんは、なんと私用の黒衣の衣装を作ってくれた。「これを着てれば目立たないから、いくらでも舞台裏を見ればいいよ」と。 以来、毎月のように私は鴈治郎付きの黒衣の一人として、歌舞伎座はもとより、全国の劇場をついて回った。 あいびきという役者用の椅子を持たせてもらい、楽屋から舞台へ、奈落から花道の鳥屋(とや)へと、鴈治郎さんやお弟子さんたちと一緒に夏も冬も駆け回った。 舞台裏で見たのは、役者たちの汗だった。花道の鳥屋で聞いたのは、鳴り止(や)まぬ拍手だった。そして、舞台で嗅いだのが、歌舞伎の、いや、喜久雄の香りだった。 さて、いよいよ最後となりますが、長きにわたりまして、この「国宝」に付き合ってくださりました読者のお一人お一人様に、心からの感謝を申し上げます。 誠に、幸せな一年五カ月でありました。 (朝日新聞 二〇一八年六月三日付)